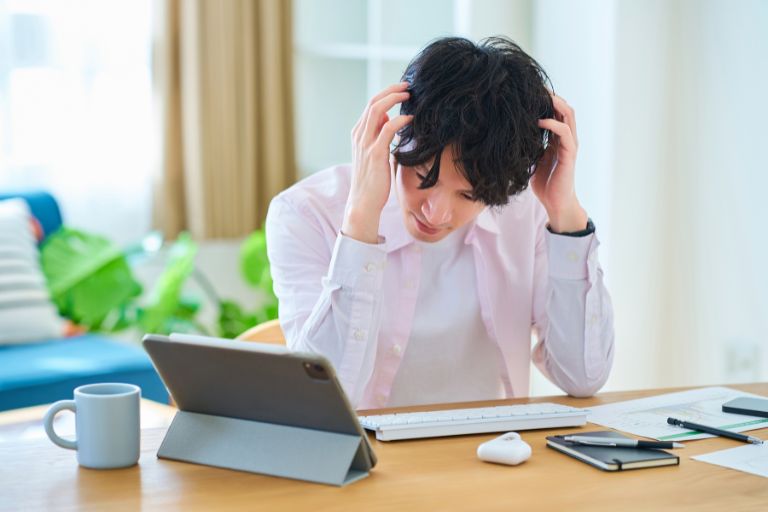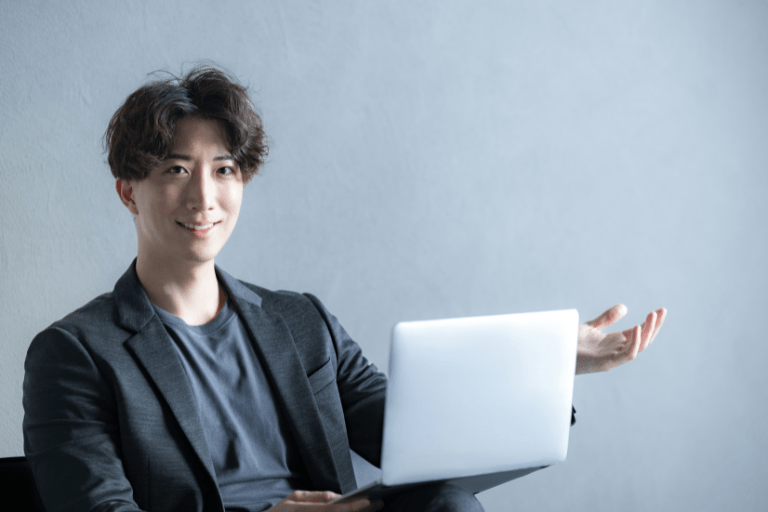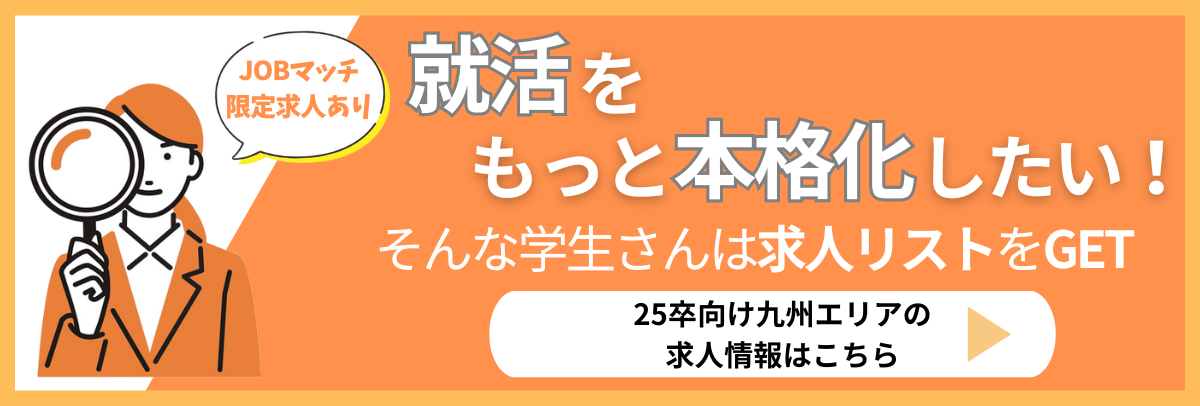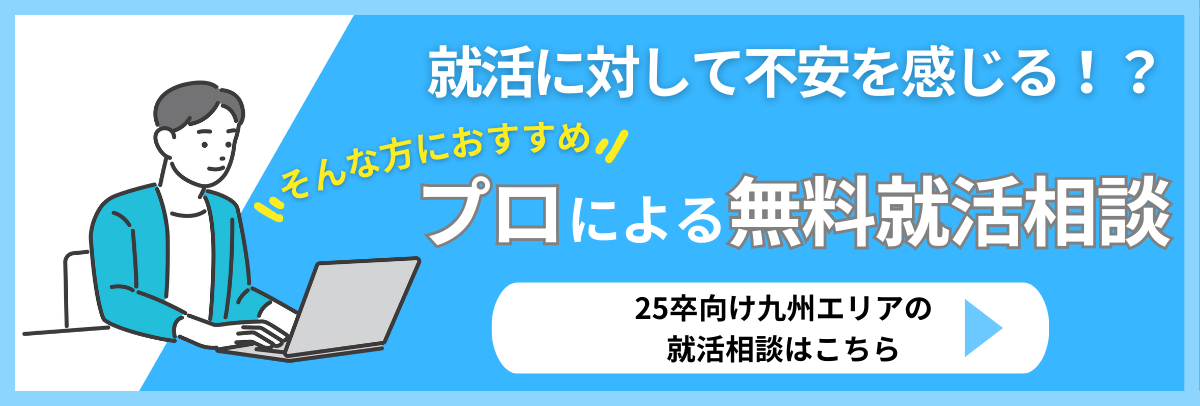「Webテストで落ちないか不安」
「Webテストの結果が思ったよりも悪かった」
「Webテストの対策が分からず困っている」
このような悩みを持っている就活生も多いのではないでしょうか。
たしかに、独特の形式や制約があり企業によって内容が異なるので戸惑いますよね。
しかし、就活のWebテストはどのテストであっても、ポイントをおさえて対策すれば落ちません。
就活生の無料相談支援を行っている「JOBマッチ」を担当している私がこの記事を担当し、各テストの対策について詳しく解説しています。
ぜひ最後まで読んで、自信を持ってWebテストに望んで就活を成功させてください。
就活のWebテストとは

Webテストとは、企業が選考の過程で就活生の能力や性格を測定する適性検査です。
パソコンからネット上で受検することから、Webテストと呼ばれています。
新卒の採用活動において、多くの企業が選考過程の一環としてWebテストを取り入れているため、就活において避けては通れません。
Webテストの目的・実施時期・受け方をそれぞれ見ていきましょう。
企業がWebテストをする目的
企業が就活生に対してWebテストを行う理由は次の2つです。
- 応募者の絞り込みのため
- 自社に合う人材を探すため
新卒採用では応募者が殺到し、大手企業などでは数百名を超えることも少なくありまません。
しかし、全員と面接するわけにはいかず、選考基準を設けて絞り込まざるを得ないのです。
選考基準として「自社にあう性格か?基礎能力はあるか?」で判断されます。
どんなに素晴らしい学生であっても、自社に合わなければ退職に繋がる可能性が高くなるからです。
Webテストが実施される時期

就活のWebテストはエントリーが開始になる頃に実施されます。選考スタートが早い企業では、大学3年の3月下旬からWebテストが実施されることも少なくありません。
ほとんどの学生は、5月初旬までに1回は受検するでしょう。
3月になるとES(エントリーシート)の記入や企業研究の本格化で忙しくなることが予想されます。また、サマーインターンに参加する学生もいるでしょう。
となれば、Webテストの受検対策は就活が本格化する前の3年生の夏前には始めておくことをおすすめします。
Webテストの受検方法
なかには企業で受検を指定されるケースもありますが、一般的には次の2つのパターンで受検します。
- 自宅で受検
- 試験会場で受検
自宅受検の場合は、メールで届いた受検案内のURLにアクセスして、期間内に受検します。
指定期間内に受検すればよいので、好きな時間に場所を選ばず受けられることがメリットです。
もちろん、自宅で受けられるからといってカンニングや替え玉受検などの不正はいけません。
一方、試験会場での受検は、指定された会場に行き、そこに準備されたパソコンを使って受検します。
メールで届いた受検案内のURLにアクセスして、指定された日時の中から希望日を選択し、当日に会場へ行きましょう。
テスト会場で受検するメリットは、Webテストの種類が同じ場合、スコアを何度も使い回せるため、高い得点が取れたら何度も受検する必要がない点です。
逆に、納得がいかない場合は、本命の受検までに複数にエントリーし、何度も挑戦することでベストスコアを更新できます。
検査内容と対策

Webテストの内容は大きく分けて次の2つです。
- 性格テスト
- 能力テスト
実際にどのようなことを問われるのか気になる人も多いと思います。ここからは、それぞれの内容を対策とともに見ていきましょう。
性格検査
就活での性格検査はあなたの人柄や性格を判断する問題です。
「はい・いいえ」で回答するのが一般的で、社会適合性やストレス耐性をみています。
学力は全く関係ないため、対策せずテストに臨む就活生がいますが、おすすめしません。
なぜなら、性格検査では企業の文化や社風にマッチしているかどうかが問われるからです。
そのため、企業が求める人材を調べておき、それに近い回答を選びましょう。ただし、同じような内容の質問が多いため、回答に矛盾を生じさせないよう注意が必要です。
能力検査
能力検査は基本的な学力を判断するテストで、次の2つに分けられます。
- 言語分野(国語)
- 非言語分野(数学)
高校生くらいのレベルなので、そんなに難しい内容ではありません。言語分野では文法力や読解力が、非言語分野では計算能力が問われます。
電卓は使用可能な場合があるので確認しましょう。
一定以上の点数が取れていなければ不合格になることがあるため、不得意分野を作らないようにするのがポイントです。
不得意分野があればどうしても解答に時間がかかり、制限時間内に終わらないことも少なくありません。
そのため、時間内に解答できるよう、問題集を繰り返し解いて問題に慣れておくことをおすすめします。
就活のWebテストの種類と対策

一口にWebテストと言ってもいろんな種類があり、それぞれ質問の仕方や難易度などが異なり、企業によって採用しているテストが違います。
したがって、それぞれのWebテストについてや、自分が志望する企業が採用しているものはどれなのかを知っておくことが重要です。
最後に、就活で採用されていることが多いWebテストを紹介します。
SPI総合検査
就活で最も多くの企業で採用されているWebテストです。自宅受検・センター受検に加えて指定会場でのペーパー受検もあります。
1問ずつ制限時間が設けられているため、スピーディーに解くことがポイントです。
制限時間は、能力検査:35分、性格適正:30分となっています。
【対策】
言語問題は、熟語の意味や文の並べ替えが問われる問題が多いため、言葉の意味を覚えましょう。
非言語問題は四則演算や確率、グラフの読み取りなどが出題される傾向で、公式を覚えただけでは解けない問題も出題されるため、参考書で学習した方がよいでしょう。
玉手箱
玉手箱はSPIの次に多く採用されているWebテストです。金融・メーカー・食品業界などで多く採用されています。
難易度はSPIよりも高く、問題数は多めで解答時間は短いのが特徴です。
SPIのように1問ずつの制限時間はありませんが、「9分で50問」といった時間配分になっています。
【対策】
後半になるほど、問題が難しくなるので時間配分を意識して解答することがポイントです。
問題数は多いですが出題ジャンルは少ないため、参考書で数多くの問題を解くことで、解法パターンを覚えましょう。
GAB
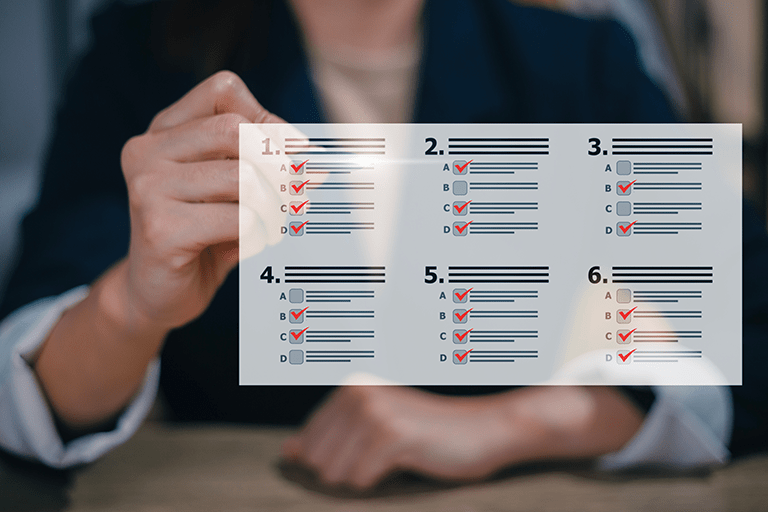
IT企業や証券会社、総合商社の営業職や研究職で採用されることが多く、とても難易度の高いWebテストです。
バイタリティやチームワークなど9特性および、営業や研究開発など将来のマネジメント適性を7つの職務適性について予測します。
問題数が多く時間は短いのが特徴で、自宅受検の場合は英語も出題されます。
制限時間は25分で52問(言語)35分で45問(非言語)
【対策】
とにかく、問題数が多いので、限られた時間ですばやく解く練習をしておくことが重要です。
CAB
CABはプログラマーなどIT技術者向けのテストです。IT業界ではほとんどの企業が採用しています。
種類は、ペーパー形式の「CAB」とWeb形式の「WebーCAB」の2つです。問題は「暗算」「法則性」「命令表」「暗号」の4項目と性格検査が出題されます。
命令表は図形を変化させる問題が出題されるなど、かなり難易度も高いのが特徴です。
制限時間は「9分で50問」で玉手箱と同じ時間配分となっています。
【対策】
「暗算」「法則性」「命令表」「暗号」「性格検査」しか出題されないので、参考書などで過去問を解きましょう。
TG-WEB
特殊な問題が多い「従来型」と図表の読み取りと計算問題が中心の「新型」の2種類があります。
問題に癖があり、特に非言語の問題は暗号の解読など、他のテストよりも独自性が高く難しい内容となっています。
コンサル会社やマスコミで多く採用されている傾向です。
【対策】
TG-WEBを採用しているとわかっていても、新型か従来型かがわからなければ、どちらのタイプも対策しなければなりません。
問題集を何度も解き直して、問題形式に慣れが必要です。
まとめ

就活のWebテストは多くの種類があり、難易度や問題の傾向も異なります。
そのため、自分が応募する企業がどのWebテストを採用しているのかを調べ、テストの特徴をつかんで勉強すれば、ボーダーラインのクリアは十分可能です。
毎回、同じような質問が多いので、問題集やアプリなどで例題を何回も繰り返して解き、傾向を把握すれば得点できます。
また、練習の際には、本番を想定して制限時間を設けて行うことが大切です。
Webテストの対策をして就活を成功させましょう。